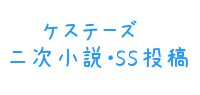34
ゼロと双剣の使い魔 35
「旦那、貴族の旦那。うちはまっとうな商売してまさぁ。お上に目をつけられるようなことなんかこれっぽっちもありませんや」
「客よ」
「こりゃおったまげた、貴族が剣を!」
「・・・なによ?」
ルイズはいきなり不機嫌そうな声に変える。
「い、いえ、兵隊は剣を、貴族は杖をと相場は決まっておりますんで」
「使うのはわたしじゃないわ。使い魔よ」
「剣をお使いになるのはそちらの方で?」
ルイズは頷いた。
「私剣のことなんかわからないから適当に選んでもってきて」
主人はさっさと奥の倉庫に消えていった。
主人が奥に引っ込む瞬間、『鴨が来た』とかすかに聞こえた気がしたロイドは倉庫の入り口を見て首をひねった。
(聞き違いか?)
店の中を見まわっていたロイドがルイズの傍までくる。
「・・・なあ、ルイズ、どうしたんだ?いきなり不機嫌そうに」
「別になんでもないわ。ただ、なんとなくこれからムカつくことが起こりそうな予感がしただけよ」
「いや、それだけの理由で不機嫌になられても」
ばたん!
いきなり扉が開く音がして振り返ってみるとそこにいたのはよく知っている人物、キュルケとタバサだった。
「ルイズ!いくら自分の魅力に自信がないからって物で釣ろうなんてラ・ヴァリエール家も落ちたもんね!」
「・・・予感的中ってわけね。いきなりやってきて何言ってんのよ。ていうか、なんであんたたちがここにいんのよ」
「もちろんあなたたちの後をついてきたからよ」
「勝手につけてくんな!!!」
「おや?これは珍しい。貴族の方がまたおいでなさった」
主人が一瞬ニッと口をゆがめた気がしたが、普段あまり人を疑わない性格のロイドは見間違いかなと思っただけだった。
「これなんかいかがです?」
そう言い持ってきた剣を見せた。
見ると、見事な剣だった。
1.5メイルはあろうかという大剣だった。柄は両手で扱えるように長く、立派なこしらえである。
ところどころに宝石がちりばめられ、鏡のように両刃の刀身が光っている。