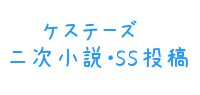3
ゼロと双剣の使い魔 4
「あんたの左手の甲に刻まれた文字あるでしょ?それが契約の証しのルーンよ。そして、使い魔はご主人様に一生仕える下僕よ。感謝しなさい、貴族に仕えられるなんてそうそうあったもんじゃないんだから」
ルイズはロイドにとって初めてのタイプだ。自分勝手で相手の都合を全く考えようとしない。
ロイドのいた世界でもそういうやつは確かにいた。しかし、ルイズのはそれ以上だった。
「ふ、ふざけるな!!使い魔だとか下僕だとか人のことを考えようともしないで自分勝手に話進めて!!」
「なによ、その口のきき方。貴族に対する礼儀がなってないんじゃないの?それにこっちで食事とかどうするつもりよ。私が養ってやらなくちゃすぐ餓死するんじゃないの?」
「貴族が何だって言うんだ!!それに、俺だって好きで来たんじゃない!!お前が呼んだんじゃないか!!」
「私だって好きであんたなんかを呼んだんじゃないわよ!」
2人はにらみ合い、いつ掴みかかってもおかしくないような状態だった。
そして、それをおさめたのはオスマンだった。
「落ち着きなさい2人とも。ミス・ヴァリエール、今のはお主が悪いぞ。使い魔とて生きているんじゃ。それを物のようにむげに扱っていいものではあるまい。先ほどの会話の中から、お主がいつも言う貴族らしさというものが見つけられるか?」
「・・・いえ、すみません」
まだ納得しきってない様子のルイズだったが、とりあえず言い過ぎたと思ったのかしぶしぶ謝ってきた。
「ふむ、それでロイド君、君には頼みがあるのじゃ」
「頼み?」
「ミス・ヴァリエールの使い魔をやってはもらえんか?もちろん一生というわけではない。君が元の世界に帰るその時まででいいんじゃ。もちろんこちらもできる限りのことはするつもりじゃ。君が元の世界に戻るための手段も探してみるつもりじゃ」
ロイドは考え込む。確かにこの地に詳しくない自分が生きていくにはオスマンの助けは必要になるだろう。
元の世界に戻るための方法も探してくれるという。
「・・・わかった。その条件、のむよ」
「そうか、ありがとう。じゃが、最終的に見つからんでも恨まんでくれよ?なあに、こっちの世界も住めば都じゃ。嫁さんだって探してやるよ」
「・・・そうならないように願ってるよ」
オスマンの砕けた言葉づかいに少しだけイライラしていた気持が和らいだ気がした。
その会話を最後に、ロイド達は席を立った。